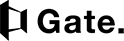ご導入企業様からの声

小田急不動産株式会社
仲介事業本部 仲介営業部 企画推進グループリーダー
2022年7月に収益不動産用サービス「LIFE SCAPE1(ライフ スケープ ワン)」をリリース。
リーウェイズが提供する不動産DXコンサルティングの先進事例として、小田急不動産株式会社の山尾様にお話を伺いました。
「LIFE SCAPE1」サービスサイト
https://ls1.odakyu-chukai.com/
御社の事業内容について教えてください。
小田急不動産は、総合的に不動産業を手がけており、実需向けの売買仲介に加え、投資用不動産を中心とした広域的なアセットビジネスも展開しています。特に、大口案件を中心としたアセットやフィービジネスは、沿線に限らず全国規模で展開しているのが特徴です。
今回プロジェクトを始めるきっかけとなった課題感について教えてください。
小田急不動産は、プロ同士の大口取引をまとめる実力のある会社ですが、一般の方には「小田急といえば小田急線沿線の住宅を扱う会社」というイメージが強いので、投資用不動産を全国展開していることはあまり認知されていませんでした。
これまで投資用不動産については、既存の営業チャネルを通じて対応してきましたが、投資に特化した自社サイトがなかったため、Web時代における情報発信や集客に課題を感じていました。そこで今後のWeb対応の強化に向けて、リーウェイズのマーケットデータを活用した自社のWeb集客力を高める支援をお願いできないかと考え、Web戦略策定のコンサルティングを依頼しました。
自社の課題やニーズを明確にしていく中で、ライフシミュレーション機能の導入をご提案いただき、2022年7月に新たなサービスサイト「LIFE SCAPE1(ライフ スケープ ワン)」を立ち上げました。その後SEOを意識した集客施策として、「TERAKO(テラコ)」というメディアから一般の方にも分かりやすい記事を配信する形で展開しています。

事前にさまざまな企業のサービスを検討されていたかと思いますが、弊社に最も魅力を感じたポイントを教えてください。
一番大きかったのは、やはり「圧倒的なデータ量」です。また、不動産テックという言葉が世の中に広がるずっと前から、地道にデータを蓄積してきた点に時代を先取りする姿勢を感じました。その点は他社には置き換えられない強みだと感じました。実際にビッグデータがあることで、精度の高い分析が可能になり、投資家が納得して意思決定できるような、信頼性のある判断材料を提供できるという点で、非常に重要だと考えています。
初めてリーウェイズのサービスを見たときの印象はいかがでしたか?
「非常に先鋭的だな」というのが率直な印象です。 情報が時系列に整理されていて、直感的に「使いやすそうだ」と思いました。不動産テックと言えども、実際に業務で使うとなると難解なツールも多い中で、「Gate.」は操作性や視認性の面でも優れていると感じました。加えて、当時の巻口社長のプレゼンテーションも印象的でした。不動産業界の透明性を高めたいという思想や、「市場全体が信頼できるものになるべきだ」というメッセージに非常に共感しました。
その思想は「Gate.」にも反映されていて、良いことも悪いことも含めて、誠実に情報を可視化し伝える設計になっています。「AIはこう分析している。それに私たちの知見を重ねる」。プロとして蓄積してきたノウハウに、リーウェイズのテクノロジーが加わることで、「より信頼性のある提案」や「働きがいのある業務」にもつながっていくと感じました。
「LIFE SCAPE1」を立ち上げてから、具体的な成果が出たという実感があれば教えてください。
最大の成果は、ビッグデータを活用した投資用不動産の特化型Webサイトを新たに立ち上げ集客を強化できたことです。実際にサイトを公開してみると、想定以上の反響がありました。特に「すぐに査定結果が出て便利」「根拠が明確で安心できる」といったお声をいただいており、WEBサイト経由でのお問い合わせも増加しています。新たな集客サイトを構築するにあたり、Gate.のような信頼性のあるデータ基盤があったことは非常に大きかったです。
また、「LIFE SCAPE1」と並行して立ち上げた不動産投資オンラインメディア「TERAKO(テラコ)」も着実に成果を上げています。立ち上げ当初は「どんなコンテンツを出せばユーザーに見てもらえるのか?」という手探りの状態でスタートしましたが、試行錯誤を重ねた結果、現在では社員によるコラム記事など、知識や専門性を活かしたコンテンツが非常に好評です。実際に、コラムをきっかけに「LIFE SCAPE1」への訪問が増えたというデータもあり、着実に「見てもらえるWEBサイト」へと成長していることを実感しています。
正直、最初は「本当に効果が出るのか?」という気持ちも少しありました。ただ、我々としてもターゲットや登録者数などの目標を立てて誠実に取り組んでおり、実際に運用を開始してみると、当初の予想を大きく超える反響がありました。成果として目標数値に対して200%以上の反響を獲得し、私たち自身も驚いています。
2022年7月にスタートして3年を迎えますが、お客様からの反応も目に見えて増え、社内にもポジティブな変化が生まれています。

左:リーウェイズ 大場 右:小田急不動産 山尾様
社内メンバーの反応や、サービス導入後に生まれた新たな気づきについて教えてください。
当初、私たちの事業領域は「全国対応は難しいのではないか」と考えていましたが、実際には都心部や地方都市からの反響が増え、社内でも驚きの声が上がっています。例えば、これまで積極的に対応してこなかった名古屋や大阪といった小田急沿線外の地域からもお問い合わせがあり、新たな事業の可能性を感じる社員も出てきています。
コラムなどのコンテンツを通じて、私たちの考え方や取り組みが伝わるようになり、地方都市からの反響も増えたと考えています。現在、月に1万人ほどの方にご覧いただいており、投資家向けの専門情報だけでなく、一般の方にも分かりやすく発信を心がけていることで「信頼できる会社」という印象にもつながっていると感じています。
直接営業していないエリアからの期待の声が届くことで、「この仕組みを使えば全国的な広がりも可能だ」という認識が社内にも芽生え始めており、事業拡大のきっかけになっていると感じています
テック導入について社員からの反発はなかったでしょうか。
投資用不動産の分野では、専門性や数字に基づいた判断が重視されるため「感覚よりもデータに基づいた提案を行う」という文化が根付いていたこともあり、不動産テックの導入に対してはスムーズに受け入れられました。ベテラン社員の経験やスキルを活かしながら、テクノロジーによってその価値をより明確に伝えられるようになったと感じています。また、新人にとってもテクノロジーは成長を支える基盤となります。根拠ある分析や提案を行うための足場として、ベテラン・若手を問わず活用できるのが、テック導入の大きなメリットだと思います。
今後、注力していきたい事業領域や取り組みについて教えてください。
今後は「物件購入」に関するお手伝いにも、力を入れていきたいと考えています。これまで当社はビッグデータを活用して「売却物件」に関する集客を強化してきており、一定の成果も得られているのですが、それに加えて、購入を検討されているお客さまの集客も強化していきたいという意向があります。
背景としては、投資用不動産の売買においては、物件の入れ替えや税務・相続といった観点でのニーズがあり、これまでは売却中心の支援を行ってきました。しかし今後は、購入希望者に対しても適切な物件提案を行える体制を強化し、売却と購入の両面でお客様のニーズに対応できる仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えています。
そのために、Webサイトのあるべき構成や、Googleからの評価を高めるための仕組みづくりについて、改善を進めているところです。
投資用不動産のマーケットは、一般媒介などで表に出にくい物件も多く、見えにくい部分が多いのですが、売却側で一定の成果が出てきた今、購入側でもやれることがあると感じています。

「LIFE SCAPE1」が目指す理想のサービス像や、お客様にどのような価値を提供していくのかについてお聞かせください。
人生100年時代、資産運用の選択肢として不動産はもっと広く活用されるべきですが、不動産投資は、まだ世の中には「怪しい」「騙されそう」というイメージが根強くあります。私たちはそれらを払拭していきたいと考えています。日本ではいまだに現預金が中心ですが、それでは資産が目減りするリスクもあります。不動産投資がもっと納得感のある、誠実な提案の中で選ばれていく市場にしたいと思っています。
我々のサイトを使っているのは個人投資家の方が中心で、最初は物件の比較や入れ替えなどをしながら資産形成を始める方が多いです。その後、機能の高度化や知識提供を通じて、次のステージへと進むお客様も出てきています。小田急としては、鉄道事業を通じて長期的にお客様と関わってきた文化があり、不動産事業でも「一度きり」ではなく、人生の節目ごとに寄り添いながら、長期的な関係性を築いていきたいと思っています。そして、AIやビッグデータを活用しながら、定量的な裏付けのある提案を行い、お客様が安心して判断できるようなサポートをしていきたいです。
テクノロジーで効率化するだけでなく、「信頼」を軸に、社会に貢献できる企業であり続けたいと考えています。